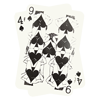「あぁ、マサ君。そげんに突かれると、うち壊れてしまうばい」
「あぁ、マサ君。そげんに突かれると、うち壊れてしまうばい」
泣きながら、薫は正朝に身体を揺すられた。
「あぁ、きっつい。あぁ、ああーん」
正朝が自分のすべてを薫の身体のなかに噴射した。
薫はいたぶられた、うさぎのようだった。泣き顔を枕に隠した。
「ごめん、ごめんな、薫」
正朝は泣いている薫に、どこか自己嫌悪を感じ、そしていとおしさを感じ、今度はそっと薫を抱きしめた。
疲労と虚脱にまとわりつかれながら、正朝はずっと薫を抱いていた。夜は静かだった。
やがて正朝は墜落するように、眠りに就いていった。
7月12日。午前11時。目覚めると薫の姿はなかった。
冷蔵庫の扉にマグネットで貼り付けた置き手紙があった。
「マサ君、何かつらいことがあったのでしょうか。私まで悲しくなります。黙っているマサ君は格好良いけれど、たまには私にも悩みを話してください。それじゃあ学校に行って来ますね。冷蔵庫に朝食があります。食べてね。そして今夜も勝ってね。薫」
冷蔵庫を開けた。サンドイッチがラップに包まれていた。
切り分けられたメロン片が皿に盛りつけられて、それもラップに包まれていた。
正朝はサンドイッチをつまんだ。焼きベーコンとレタス、トマト、スライスチーズがはさんである。別のサンドイッチは粉砕したキュウリとみじん切りにした人参をマヨネーズで和えた具がはさんであった。
メロン片を手にした。
ゆうべ自分が食べなかったメロンを薫はカットして皿に盛りつけておいてくれたのだ。
優しい女だと思う。可愛い女だと思う。
今夜はシャトーで夜番だ。少なくとも明日の昼まで薫はやって来ない。
そう思うと、無性に薫に会いたくなった。
しかし携帯電話の番号も、メールアドレスもお互いに知らせてはいないのだ。
それは正朝が望んでそう取り決めたのだった。
自分の世界に他人が入り込んでくる煩わしさ。それを正朝は嫌っていた。
―他人が入り込んでくる?。
薫は、まだ自分にとって他人だというのだろうか。
サンドイッチを食べながら、正朝は薫を想い続けた。
―いかん。気がそがれる。カジノの勝負に支障をきたす。
いつものようにテーブルを取り出すと、シャッフルの練習をする正朝だった。
午後6時までカードをさばく練習を続けた。
窓の外には天気予報が告げたように雨が降っていた。
午後7時にマンションを出た。雨はあがっていた。
「だが、湿気はまだ残っているな」
カードさばきは重たくなる。シャトーの店内はエアコンが効いているが、微妙な湿度の差はカードの紙片にも影響する。それを心して正朝はシャトーに向かう。
道すがら、天神中央公園西側の屋台『姫ちゃん』でラーメンと餃子の夕食をとった。
屋台から席を立って、公園沿いの道を中洲に向かう。
みすぼらしい老人が、手押し車に空き缶を満載して歩いて来た。
さっきまでの雨除けなのか、透明なビニールの合羽を着ている。透けて見えるランニングシャツは汚れている。スボンも拾いものなのかダブダブで汚れだらけだ。裸足に大きな靴を履いている。捨てられていた靴なのだろう。皮は皺だらけで、紐は切れている。
無精髭が伸び放題だった。髪も切っていない。ホームレスなのだろう。薄汚い老人だ。
正朝と狭い道をすれ違うとき、ホームレスの老人は手押し車が正朝に当たらないようにと舵を切り、よろけて転びそうになった。
「しゅ、しゅいましぇん」
それが老人の発した言葉だった。
おそらくすれ違う誰にも、そうして謝って歩いているのだろう。
老人は、まだ正朝にペコペコと頭を下げていた。
正朝の心のなかは怒りに満ちた。
老人に対して怒っているのではない。
やるせなさに対して怒りがこみ上げてきたのだ。
この老人がどんな人生を過ごしてきて、そして今やホームレスとなったかは知らない。
しかし、そんなに謝ることはないではないか。
そんなにもおびえたように頭を下げ続ける必要はないではないか。