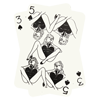賀代子は手を振って男を見送った。カーテンの内側に正朝たちがいることには気がついていない様子だ。正朝は気がつかれないように小声で言った。
賀代子は手を振って男を見送った。カーテンの内側に正朝たちがいることには気がついていない様子だ。正朝は気がつかれないように小声で言った。
「由佳里さん、あんたの部屋に戻っていいかな」
「よかよ。何で?」
「シッ」
正朝は何も知らない由佳里が不思議そうに声をあげるのを制した。
3階の由佳里の部屋で、正朝は聞き取った話の一部始終を声をひそめて由佳里に話した。
「詩音ちゃん……。そげな男に騙されて……。それも北朝鮮から逃げてきたなんて……」
由佳里は憤っていた。
「あたしらは、自分の意志でソープ嬢になっとう。生活も気ままたい。そういえば詩音ちゃんは、こん店のひと部屋を住まいにしとうと。賀代子しゃんが、おにぎりやら、カップ麺やらを渡して、それを食べとうもん。生活は気ままじゃなかけんね。なして、そげん生活ばして、サービス料も賀代子しゃんに取りあげられとうか不思議やったけれど、そん話で合点がいくとよ」
由佳里も声をひそめていた。
「そんで、どげんすると?」
正朝はマルボロをくわえた。スッと由佳里がライターの火を差し向けた。
「俺はそもそも詩音のお守りを届けに来ただけだ」
正朝はマルボロの煙を吐き出した。
「冷たかね、正朝しゃん。詩音ちゃんを、何とか救うてあげる手立てはなかかね」
だが、正朝は何とも返事をしなかった。
正朝は由佳里の部屋を出た。由佳里と一緒に1階の待合室フロアに降りた。
わざとらしく明るく大きな声で由佳里が見送りの声をかけた。
「ありがとうございました。またんお越しばお待ちしております」
その声でカウンターの奥から賀代子が飛び出して来た。
「まぁ、お客しゃん。これがらも、由佳里ちゃんばご贔屓にしちゃってください」
賀代子は化粧の濃い丸顔に精一杯の作り笑顔で正朝に言った。
正朝は、左手を軽くあげて、店をあとにした。すでに夜闇が町を包んでいた。
中洲1丁目から、わずかな距離を歩いてシャトーに向かう。
―どうする。詩音、いやミソンの身の上を……。
聞いてしまった。知ってしまった。正朝の心は揺れていた。
由佳里は本気でミソンの身の上を案じているようだった。
それでも、
―俺には、関係のないことだ。
そうも思う。それが自分の生き方だ。そう思う。
そう思ううちに、シャトーの店前にたどり着いた。
「甘味を摂るのを忘れちまった」
午後8時30分。川端町の商店街は閉まっている。
正朝は川端町のコンビニでチョコレートを買った。
夜の那珂川を眺めながら、チョコレートをかじった。
気がついたら川端飢人地蔵尊のほこらの前に歩み着いていた。
初めてミソンに会ったときのミソンの言葉が甦った。
「飢えている人、おおぜい……。私、食べられない、これ」
あれは、北朝鮮に暮らす人々のことを思いやった言葉だったのだ。
身体が熱くなっていく。そんな感覚を覚えたことはない。だがどうしても怒りに似た感覚が正朝の身体を熱くしてゆく。
「俺には、関係のないことだ」
身体の感覚とは真逆に、正朝は考えていたことを思わず言葉に発した。
自分でも独り言を叫んだことに驚いた。
―いけない。こんな動揺した心のままではカジノのディーラーは務まらない。
地蔵尊の前から逃げるように中洲の繁華街のネオンの奥にあるシャトーへと急いだ。
その晩の正朝は、負けた。店側の損失は300万円を超えた。控え室に戻った。隆史が、
「どげんした。久しぶりに切れが悪か。お前らしくもなかと」
と正朝の肩を叩いた。純平が言った。
「マサ兄ぃ、午前5時に仕事が明けたら、肩ば治しにソープでも行きますか」