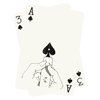薫の声だった。時計を見ると午後3時だった。玄関のドアロックを解除する。
薫の声だった。時計を見ると午後3時だった。玄関のドアロックを解除する。
しばらくして薫が部屋にやって来た。
プラダのオーク色のワンピースを着た薫が、手に大きな籠を下げている。
ショートカットの黒髪がフワリと揺れた。
「柳橋連合市場で買い物してきたとよ。マサ君には栄養をつけてもらわんと」
薫は籠のなかから、まずエプロンを取り出してワンピースの上に着た。
「胡麻サバと、がめ煮ば、作ってあげるけんね。座って待っとって」
柳橋連合市場とは春吉1丁目の住吉通り沿いにある街なかの市民市場だ。
魚を中心に生鮮食品が店舗に並ぶ。明太子を売る店も多い。何より安い。
住吉通から西に15分も歩けば薬院にたどり着く。
薫は新鮮な魚や野菜を買って、住吉通を歩いて来たのだろう。
まったく自炊をしない正朝にとって台所は水を飲む場所でしかなかった。
その台所に薫が立っている。自分の部屋が一変したかのような光景だった。
まず食卓に現れたのは、おきゅうとだった。
「他の料理ができあがるまで、おきゅうとをつまんで待っとって」
と薫が鯖を三枚におろしながら言った。
おきゅうとはエゴノリという海草を乾燥させ、煮溶かして固めた料理だ。
蒟蒻とも寒天とも違う。エゴノリそのものには味はない。
だが福岡の食卓には欠かせない食べ物なのだ。味付けも家庭ごとに異なる。
薫の出したおきゅうとは、すり胡麻と醤油のたれに漬けられ、きざんだ博多ネギが乗せられていた。
次に運ばれてきたのは、胡麻サバだった。鯖の一種ではない。確かに全国にはゴマサバという種類の鯖が味わわれている。しかし福岡で胡麻サバといえば郷土料理である。
他の地方では、鯖はしめ鯖や塩鯖にして食べる。腐るのが早い魚だからだ。
その鯖を刺身で食べるのが福岡の胡麻サバだ。新鮮でないと作れない。
すり胡麻に醤油、砂糖、酒、ミリンを加え、刺身にした鯖と和える。
薫は備前焼の盛り皿まで持参していた。褐色のざらついた備前焼の大皿に、紫蘇の大葉を敷きつめ、その上に胡麻サバを盛りつけた。手ちぎりの細かい海苔を散らしてある。
「もうすぐ、がめ煮ができるけんね。先に胡麻サバ食べて待っとってね」
薫の大きな籠からは有田焼のご飯茶碗まで出現した。薫はレンジで温めた米飯を、青と白のコントラストが美しい有田焼の茶碗に装って、正朝の前に差し出した。
がめ煮は別名を筑前煮という。里芋、人参、大根、蓮根、牛蒡、筍に蒟蒻、それに骨付き鶏肉の煮込みだ。砂糖と醤油で煮込む。
正朝は胡麻サバに箸をつけた。胡麻の香りと甘い醤油味の鯖の刺身にホッとする。
米飯も美味い。
ホッとするのは味にだけではなかった。エプロン姿の薫の後ろ姿にもホッとした。
「はい、がめ煮ができたけん。野菜はたんと食べんといかんよ」
朱色の有田焼の鉢に、根菜と鶏肉を煮込んだ、がめ煮が盛りつけられていた。
里芋、人参、大根、蓮根と正朝は箸を運んで口に入れた。家庭の味がした。
薫はエプロンを着けたまま、自分も座って両手を料理に合わせ、
「いただきます」
と言って、自分も胡麻サバや、がめ煮に箸を伸ばした。口に頬張る。
「ふ、ふふふぅ」
と薫が頬を膨らませて笑う。美味くできたでしょうという微笑に見える。
無表情だった正朝も、薫につられて少し笑った。
「あ、笑った。マサ君が笑った。うれしか、うち」
その薫の言葉に、醒めたように笑いを消す正朝だった。
食事が終わった。正朝は羅紗を張ったテーブルを部屋の中央に移動させた。
そのテーブルの上で、カードをシャッフルする練習を始めた。
しばらくは正朝の手技に見とれていた薫だったが、
「練習の邪魔ばしたら、いけんね」
と言うと、1冊の書籍を取り出して読書を始めた。
『嵐が丘』エミリー・ブロンテ著の長編小説である。
ふとカードさばきの練習の手を止めた正朝が薫に声をかけた。
「分厚い本を読んでいるんだな」