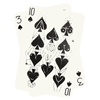「組長の口利きで、中洲のパーの雇われママを勤めている。暴力団とは縁のない、どこにでもあるバーだ。そこは組長も俺への仁義を尽くしたつもりだったんだろう」
「組長の口利きで、中洲のパーの雇われママを勤めている。暴力団とは縁のない、どこにでもあるバーだ。そこは組長も俺への仁義を尽くしたつもりだったんだろう」
インク瓶を棚にしまいながら小島は笑顔を消した。ふぅとため息を漏らした。
「その組長も再入院して、病院のベッドで死んだ。再発したガンの進行は止められなかった。“人生の最期に他人に初めて優しくしてもらった”と言って息を引き取ったそうだ。他人というのは藍田のことなのか、まさか俺のことなのか、それは分からないがな」
大介は渡された紹介状を手にジッと封筒を見つめていた。
「その組は跡目相続で内紛してな。結局2つの暴力団に分裂した。かつての勢力は失った。2派に分かれて勢力が弱まったところを、例のヒットマンを送り込んだ敵対する暴力団につぶされたんだ。だから藍田の妻が、その暴力団のヤクザに再び薬漬けにされることもなかった。任侠なんて言っても、闇社会に生きる者どもの末路なんてそんなものさ」
大介は、紹介状から視線をあげると、夕子の横顔を見つめた。
「そして俺は、その闇社会に生きる者どもの治療をするために、ここに自分の診察室を開いた。闇社会に関わって、治療を受けなければならないはずなのに、治療を受けられない人間たちが大勢いることを知ったからだ」
夕子はすすり泣きながら、小島の話を聞いていた。
「俺も、闇社会にどっぷりと足をつけちまった、やくざ相手の何でも医者だ。路上に立って客引きをする売春婦の堕胎から、薬物中毒のやくざもんの治療や、お前のように表立って医者に行けない怪我人や病人の治療まで、様々だ
夕子は大介の視線には気がつかない様子だった。
「俺には東京に息子がいる。だが俺からの連絡は絶った。息子からも連絡はない。俺は独りで、この街で闇社会の医者として生きていく」
夕子は、すすり泣きを続けていた。大介がその肩に手を回して抱いた。
「話はこれで終わりだ。だから若造。薬物には手を出すな。そして闇社会からは早く足を洗うことだ。まっとうに生きていく道は、いくらでもある。道を探せ。話は終わりだ」
小島は、診察椅子をクルリと回すと、正朝や大介に背を向けた。
大介はすすり泣く夕子を患者椅子から抱き上げて、立ち上がらせた。
正朝が診察室のドアを開けた。大介が夕子の身体を支えながら、ドアの外に出た。
看板も掲げられていない小島医院を3人は退出した。
翌5月1日は晴れた。午前9時30分、博多駅新幹線ホームに正朝たちの姿があった。
「午後2時過ぎには静岡駅に着く。そこからは山間の施設まで電車とバスの乗り継ぎだ」
大介が自分に確認するように言った。
隣には夕子が立っている。
「夕子を入院させたら、明日には帰ってきて夜番の勤務に戻る。深尾店長によろしく伝えてくれ」
大介は夕子に付き添って、小島医師が紹介してくれた静岡の薬物依存症の治療施設にまで赴くのだ。
見送りのため、正朝と純平がホームに立っていた。
「夕子しゃんが、こげんべっぴんしゃんと思わんかった。大介兄ぃが惚れるのも無理はなか」
純平が、人一倍大げさにはしゃいだように言った。
隆史はいなかった。2人が付き合うのにも反対していた隆史だったが、昨夜に正朝たちから小島医師の診察の顛末を聞かされて、そして夕子の治療入院費を大介が負担すると聞いて、ますますかぶりを振ったのだ。
「だまされとうばい。治療費を大介が支払うのは間違っとるばい。それで大介は、おなごが退院したら、もう二度とおなごに会わないだと。鼻の毛まで抜かれとうばい」
イラついたように言うだけだった。
純平の美人だという誉め言葉に、夕子は大介の背中に隠れて頬を赤く染めていた。
「大ちゃんに、こんなお友だちがいて支えてくれているなんて、うれしいです」
言葉少ない夕子が、小声で言った。
「大介兄ぃ、今夜のシャトーは僕が守りますけん。気兼ねなく行ってきてくんしゃい」
純平がおどけて言う。正朝は片手をあげて、大介とハイタッチの挨拶を交わした。
言葉は何もかけなかった。黙って、サングラスの奥から2人を見つめた。
発車を知らせるアナウンスがホームに響いて、大介と夕子は新幹線の車内に去った。
「よか、よか。こいでよかと。さぁて、俺は自宅に戻って、夜番に備えてもう一度、眠るとします」
純平がホームから走り去る新幹線を見送りながら言った。
正朝はもう背中を向けると、新幹線ホームから博多駅の階下コンコースに向かって歩き出していた。
純平は博多駅前から出ているバスに乗った。正朝に挨拶した。
「そいやい、今夜またシャトーで会いましょたい」
純平は自宅に帰っていったのだろう。
正朝はタクシーに乗り、薬院の自宅マンションに向かった。
自室のドアを開け、服を脱ぐとベッドに倒れ込んだ。時計は午前10時を指していた。
玄関のチャイムが鳴った。ビクッと正朝は起き上がると、周囲を見回した。
それが自分を誰かが訪ねてきたチャイムだと分かると心身の緊張を解いた。
―こんなときでも、俺は警戒心を捨てられない。
そう思いながら、壁に掛けられているドアホンを耳に当てる。
「遅めのお昼ご飯の出前でーす」