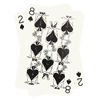「会わせろ」
「会わせろ」
隆史が言った。
「その夕子っていうソープ嬢に会わせろ。俺が話ばつけちゃる」
「いや、やめてくれよ。これは僕の問題なんだ」
「仮に話が本当やとしても、覚醒剤中毒のあすんもんぞ。惚れるなら他にもよかおなごが、いっぱいおるやろう」
隆史と大介は押し問答を交わし続けた。純平はオロオロと話を聞く。
正朝が言った。
「覚醒剤を買う金を渡し続けるより、覚醒剤から足を洗わせる方が良くはないか」
「どげんすっとかっ」
隆史が激昂したままに、正朝の横顔を見た。
「俺を治療してくれた小島先生に、その夕子さんを診察してもらっちゃどうだ」
「おおっ」
隆史が賛同の声をあげた。
正朝は言っておいて、そんな提案をした自分の言葉に心のなかで驚いていた。
以前の無関心、無感動な正朝だったら、知らん顔を通しただろう。
友情……か。それとも愛。愛か。他人を思いやる心が宿ったとしたら。
―薫に出会ったからなのか。
そんな正朝の心の葛藤をよそに、隆史は大介に言った。
「その夕子っておなごを、ルネから連れ出すことは、できるんか。どげんね」
純平は希望を見いだしたとばかりに、黙ってウンウンと首をたてに振った。
「ルネへの勤務が始まるのは午後5時からだ。その前なら、そうだな、連れ出せるかな」
「話は決まりばい。まずは本当に覚醒剤中毒か、騙されとらんか。はっきりさせんとな」
隆史はベンチから立ち上がって、大介の肩を叩いた。夜はすっかり明けていた。
那珂川には、博多湾から飛来したウミネコがニャアニャアと鳴き声を立てていた。
午後3時に、春吉の雑居ビルのエレベータに、正朝は乗っていた。大介の付き添いだ。
そして初めて会う夕子が、顔をうつむかせてエレベータに乗っていた。
小島医院のドアノブを開けたのは、正朝だった。
「その女か」
小島医師はぶっきらぼうに言った。
「ここへ座れ」
夕子にもぶっきらぼうに命じた。患者椅子に夕子がそっと腰かけた。
「お前ら、男どもはカーテンの外に出ていろ」
小島医師はサッとカーテンを引いた。正朝と大介はカーテンの外に追い出された。
「腕を見せろ」
と小島医師の声が聞こえた。
それから15分ほど診察が続いた。裸にして全身を調べているらしかった。
カーテンが開いた。小島医師が言った。
「よく連れてきてくれたな。この女(ひと)は、年季の入った覚醒剤依存症患者だ。よくここまで身体がもったものだ。施設に入所して、生活管理を受けながら、依存から抜け出す治療が必要だろう。俺が紹介状を書いてやる」
大介が身を乗り出して小島に尋ねた。
「その施設って、どこにあるんですか」
「静岡県の保養地だ。福岡からは遠いが、その施設なら信頼できる。入院費用がかかるが、その金はどうする?」
「ぼ、僕が支払います。すべて覚醒剤を買うために使ってしまって夕子には金がないし」
「依存症から完全に抜け出すまでは3ヶ月かかるか、半年かかるか。その期間の入院費となると、300万円から500万円ほどかかるぞ」
「構いません。僕が稼ぎます。もう洋服は買わない。いま貯金は50万円もないけれど、夕子が覚醒剤をやめられるんだったら、僕が働きます」
「稼ぐといっても、闇の仕事でか……。まぁいい。誰にも事情はある。俺は詮索しない」
患者椅子に夕子はうつむいて座っていた。
やがて夕子のすすり泣く声が聞こえてきた。うつむいたままだった。
「大ちゃんに……。大介ちゃんに、そこまで……。そこまでしてもらえる女じゃないよ、あたし」
正朝にとっては初めて聞く夕子の声だった。