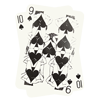小さなキッチンに立って、メロンを切り分けたのは薫だった。
小さなキッチンに立って、メロンを切り分けたのは薫だった。
「うれしか。うちへのお土産?」
薫が2つの小皿に乗せたメロンを運んでくる。若妻気取りで、はしゃいでいる。
正朝がフルーツスプーンをサクリと果肉に入れる。緑の果肉の甘い香りが広がる。
2人は向かい合って、しばらくは黙ってメロンを食べ続けた。
一切れのメロンを食べ終えて、薫が口を開いた。
「うちの親父は、この福岡で小さくはない会社を経営しとっと。家にはたまーにしか帰って来んとよ。そいが今日の昼間に親父が帰ってきたときに、母親がうちのこと“夜遊びばして、ちーっとも勉強しとらん”とか言いつけて、うちの話も聞かずに、いきなりの平手打ちたい。頬を何度もぶたれたんよ。親父だって夜遊びばかりしとうくせに」
正朝は薫を見ずに、黙ってメロンにスプーンを入れていた。
「株式会社ホリモトというても、マサ君は知らんとやろ。そいが親父の会社。裏で何ばしとっとか、親父の会社の良くない噂を聞かされたことあるもん。そいでも恰好つけて、うちを大学まで進学させたと。見栄ばい、そげなこと」
言いながら薫は立ち上がってキッチンに向かった。正朝が一切れを食べ終えていた。
察して、正朝の皿をスッと取ると、もう一切れのメロンを皿に盛って運んできた。
「堀本正、そいが親父の名前。何が正しかとね。正しいことなんかなかとよ。男らしさは娘を平手打ちすることと勘違いしとう、バカ親父たい」
薫が正朝の目の前にメロンの皿を置くのを、正朝はジッと見ていた。
「そんな風に親の悪口を言うもんじゃないぜ。どうだ、不満をぶちまけて気が済んだか」
プッと頬を膨らませて、薫が正朝の前に座った。細い顔が膨らむのを正朝は眺めていた。
薫もまた、もう一切れの自分の分のメロンを皿に盛っていた。
薫がサクリと果肉にスプーンを入れたときだった。
「俺な、来週から夜番に指名されたんだ。午後10時から午前5時までの勤務に変わる」
「えっ……」
薫がスプーンを止めた。
「そいやったら、こうして夜に会えなくなると?」
「まぁ、そういうことになる」
「でも、夜番いうたらディーラーの花形ばってんっ。マサ君、おめでとう」
ゆがんで泣きそうな顔を精一杯の笑顔に変えて薫がそう言った。
「ああ、ありがとうな」
「うち、昼間にマサ君に会いに来とう。ねっ、よかろ?」
「薫は大学に行かなくちゃならないだろう。ちゃんと学校へ行けよ」
「ううん。大学は自主休講たい。試験さえ通れば単位は取れると。うち、勉強はするけん。ねぇ、昼間に会うてくれんと?」
「薫が無理しなくても、非番は週に2日ある。その夜に会えるさ」
「2日だけなんて、淋しかもん。うち、昼間に会いに来とうと」
正朝は返事をしなかった。黙ってメロンを口に運んだ。
「そいやったら、今夜はずーっと愛して欲しか。うちのこと離さんと約束して欲しか」
愛という言葉を、こんなにも簡単に口にできる薫がうらやましかった。
自分には、愛という言葉は似合わない。そもそも愛を感じたことがない。感じたことがない……?。では目の前の薫を自分はどう思っているんだ。
やがて部屋の明かりを消した。正朝は薫をベッドに運んだ。
「ほんの少しも、ほんの少しも……離さんといて、マサ君」
これが愛か。愛じゃないのか。こんなにも自分を慕う薫を、両腕に抱きながら。
「あ、あぅーん。くっ、あぁ……、離さんでぇ」
こんなにも自分を求める薫を抱いている。
生きているとは、こういうことじゃないのか。
「マサ君の傷、こうして触れるのはうちだけたいね」
薫は正朝の腹部の傷跡を指先で愛撫しながら、つぶやいた。
薫の身体の中は温かかった。正朝は温かな薫の身体の中に安らぎを覚えた。
安らぎが、いつまでも続けばいいと思う。発憤のエネルギーが薫の身体の内部へと発射された。快感に身を任せながら、やがて訪れる脱力感に正朝は、
―落ちて行く。落ちて行く。どうせ落ちるなら、薫と一緒に……。
快感が去ると襲ってくる虚無感を正朝は払いのけたかった。安らぎだけが欲しかった。
薫は正朝の腕の中で、失神したように寝息を吐いている。
―落ちて行く。俺も落ちて行く。そうさ、薫を独りにはしないさ。
いまは薫の身体の中から降りて、その肌を両腕に抱きながら、正朝もまた深い眠りに就こうとしていた。
1週間が過ぎた。