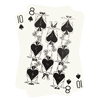「替え玉して、よかですよ。今夜は俺、おごります。マサ兄ぃの夜番復帰ラーメンばい」
「替え玉して、よかですよ。今夜は俺、おごります。マサ兄ぃの夜番復帰ラーメンばい」
正朝はハリガネを、純平はコナオトシを注文した。
どちらも麺のゆで加減のことである。コナオトシは麺を湯にくぐらせるだけ。とても堅い。ハリガネはその次くらいに堅い。そしてバリカタ、カタメ、フツウ、ヤワラカと段階を追って麺は柔らかくなる。
替え玉は、博多とんこつラーメンの食文化だろう。スープを残しておいて、麺だけを別注してスープに入れて食べる。それなら初めから麺を大盛りにしておけば良いだろうと思うが、それでは博多ラーメンの場合、麺が伸びてしまうのである。
「男は胆っ玉も、アソコも、ラーメンも堅めばい。ねっ、マサ兄ぃ」
純平はテーブルの上に置かれたニンニクを、ニンニク潰し器で丼に入れながら笑った。
「あぁー、俺。ラーメンば腹一杯に食える男になったばい」
コナオトシの替え玉を追加注文した純平は、しみじみと言った。
正朝は、返事をしないで、黙ってまだ一杯目のハリガネラーメンを食べていた。
「俺ね、ガキの頃、いっつも独りぼっちだったとですよ」
男の店員がコナオトシの替え玉を純平のテーブルに運んできた。
「久留米の隣の田主丸っちゅー福岡の田舎育ちばい。親父とおふくろは俺が小さいときに離婚して、俺はおふくろに育てられたとです。いや、育てられたと違う。おふくろは酒飲みで、いっつも色んな男のところを泊まり歩いて、俺は放っとかれましたもん。あれは育ててくれたとはいえんばい」
正朝は黙ってラーメンをすすっていた。
「博多ラーメンは、そのルーツは久留米のとんこつラーメンばい。田主丸にも、さびれたラーメン屋があったとです。俺は、おふくろがテーブルに置いていった300円ばかりを握りしめて、寒い日も、暑い日も、そのさびれたラーメン屋に晩飯を食べに行ってねぇ」
純平は、替え玉の麺を自分の丼に入れながら話を続けた。
「ラーメン一杯は食えるけど、替え玉まで注文する金は無くてねぇ。こげな食べ放題、入れ放題なニンニクとか高菜とか紅ショウガとか、スープの色が変わるほど、ぶち込んで、そいで腹ば、満たしていたとです。ひもじかったぁ-」
純平は話を続けるために急いで麺を口に掻き込んでいた。
「ある晩、いつものようにラーメン屋に行ったら、俺のテーブルからニンニクとか高菜とか紅ショウガとか、入れ放題のはずのおかずの器が、ラーメン屋のおばちゃんの手でサッと片付けられたとです。毎晩、おかずばてんこ盛りにして、替え玉ば注文せん、貧乏なガキには、サービスなんかできんということでしょう。悲しか俺のガキ時代の思い出ばい」
純平はおどけて両目に左腕を当てて、涙を拭くふりをした。
「俺、大人になったら、おのれで稼いだ金で腹一杯、ラーメンの替え玉も注文して、腹一杯、食えるもんになりたかったとです。あの晩は雪の夜やったなぁ。俺、靴下も買ってもらえんと、サンダルに裸足で、そのラーメン屋から泣きながら帰ったとですよ。木造アパートの部屋に帰っても、おふくろはおらん。だから独りで泣いとったとですもん」
正朝は、1人でしゃべり続ける純平に返事もしなかった。
「雪の夜といえば、マサ兄ぃが刺されたのも今年の冬の雪の明け方やったですね。もう傷は良くなったとですか」
声をひそめて尋ねる純平に正朝は、たったひと言を返した。
「早く、食べろ。麺が伸びちまうぞ」
「あっ……。しゅいましぇん」
何かに気がついたように純平は言葉を閉じた。触れてはいけない話題だと気がついたのだろう。純平は叱られた子どものように、黙々とラーメンをすすり始めた。
―こいつ、ガキの頃、こんな顔で独りラーメンを食べていたのかな。
正朝は思ったが、何も言わなかった。
2人はラーメン屋の前で別れた。
「マサ兄ぃ、俺が夜番に回してもらえるように祈っとってください」
純平は、そう言ってまた中洲の方角に道を戻って行った。
どこに純平は暮らしているのか。正朝は尋ねたことはないし、知ろうとも思わない。
春吉2丁目から薬院までなら直線距離にして800メートルほどだ。
渡辺通3丁目から2丁目を通り抜ければ、薬院にたどり着く。
午後11時30分過ぎに、正朝は深夜営業のスーパーに寄ってマスクメロンを買った。
甘味は頭脳を冴えさせもするが、疲れた身体を癒やしもする。
だが期するところは、別にもあった。いや期待してはいけないことだ。
―今夜、薫が待っていてくれたら、土産だと言って一緒に食べよう。
薬院のマンションが近づく。
期待する気持ちはないはずなのに、正朝の目は薫を探していた。
いた。薫がマンションの玄関に座り込んでいる。スーツを着替えているのだから、いったんは自宅に戻っているのだろう。だが薫は顔を座り込んだ自分のひざの中にうずめていて、近づいて来る正朝には気がつかないでいた。
「どうした」
声をかける正朝にハッとしたように薫は顔をあげた。
「あ、マサ君」
薫は涙で頬を濡らしていた。
「親と言い争いをしたとよ」
「そりゃ、夜中に帰らないで、俺とこうして過ごしているんだ。親は心配するだろうさ」
「しゃーしか、あのバカタレ親父」
「玄関で話し続けるのは近所迷惑だ。続きは部屋で聞く。ほら、メロン買ってきたぞ」
正朝は薫を抱き起こすと、マンションの自分の部屋に向かった。